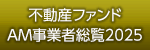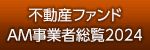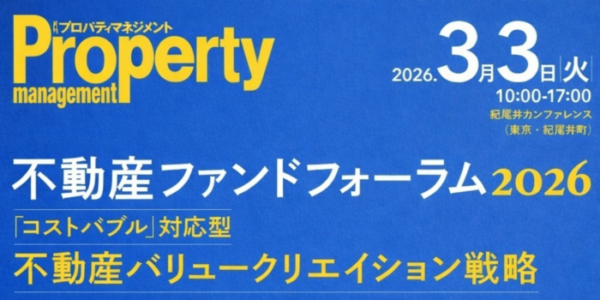――アジラ「AI Security asilla 」「asilla BIZ」
防犯カメラが“資産”に変わる
AIが導く、不動産価値の最大化
【試し読み】
施設運営に必要な人件費の高騰が止まらないなか、警備員にかけるコストを抑えながら施設の安心・安全を強化するにはどうしたらよいのか。AIテック企業のアジラが提供するシステムは、こうした悩みを解決し不動産価値の維持に貢献するばかりか、収益の拡大すなわち不動産価値の向上までもたらすかもしれない。
施設の安全性だけでなく
収益を高めるヒント提供
アジラは、AI 技術を活用した警備システム「AI Security asilla」などを開発・販売する企業。国内の大手デベロッパーやREIT運用会社が同社のシステムを採用しており、「サンシャインシティ」「グラングリーン大阪」など国内150施設以上に導入されているほか、海外の施設でも徐々に採用が始まりつつある。
AI Security asillaは、防犯カメラに映った館内の異常事態(転倒、侵入、暴行など)をAI で検知、防災センターや巡回中の警備員へただちに通知するシステムだ。しばしば発生してきた異常事態の見逃しを防ぎ、対応スピードを向上させる効果がある。また防犯カメラに映った人流や異常事態をデータベース化・分析することで、適切な警備員の数や配置場所、シフトを割り出すこともできる。
ある導入施設では、異常事態発生から警備員到着までの所要時間を1/3に短縮、警備員の巡回業務を1/3に削減した。「録画したまま放置されがちな防犯カメラ映像を有効活用し、異常事態の事前予防と即時対応を実現する」(代表取締役CEO 兼 COOの尾上剛氏)。
![[図表1]異常検知から通知の流れ](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/11/75e53d4448e1e2458319d198b7c42715.jpg)
![[図表1]異常検知から通知の流れ](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/11/75e53d4448e1e2458319d198b7c42715.jpg)
そのほかのシステムとして、防犯カメラを警備以外の使い道に援用する「asilla BIZ」というものもある。これは防犯カメラ映像から施設内の来館者数とその属性を計測・分析するシステムで、商業施設におけるMDやリーシング戦略の再考、イベントや屋外広告の効果測定に役立つ[図表]。またトイレの利用状況を計測・分析して清掃の頻度やタイミングを最適化することもできるという。
「asilla BIZに関して言えば、別途センサーの取り付けが必要な他社製品より手軽。警備体制の最適化によるコストダウンと商業施設の運営改善による収益アップ、いわば “ 守り” と“ 攻め” を両立できる点が、導入先企業から支持される理由」と同氏は胸を張る。
![[図表2]データ分析活用例](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/11/b21aa6e7a5229bdbdbdb6524b66d20f0-400x229.jpg)
既設の防犯カメラを流用可能
独自の先進AI技術を核に世界へ
導入ハードルの低さもアジラのシステムがもつ特徴のひとつ。防犯カメラは既設のものを原則そのまま使用でき、初期費用は0円である。
ユーザーは導入後に、映像データ処理に必要なサーバーの月額使用料を支払う(カメラ30台分の処理性能をもつサーバーと50台分の処理性能をもつサーバーで価格は異なる)。その料金は「警備員1人分の人件費を下回る程度」(尾上氏)だという。ひとつの契約でAI Security asilla とasilla BIZ の両方を使用できる。
システムの導入と操作、データ活用に関する相談は、アジラ社内のカスタマーサクセスチームが対応(費用は月額使用料に含む)。また有料オプションとなるがデータ分析のレポート作成代行サービスも提供している。
システム導入に最も適した不動産は、オフィスと商業が複合した大規模ビルだ。そのほかPM担当者や警備員が常駐しない中小規模ビルも、異常の通知を統合管理拠点に届ければ対応速度が増すと考えられるため、導入に適しているとする。
ところで、ここまで紹介したシステムの基盤となる技術についても簡単に触れたい。アジラは映像情報から人の動きを解析する「行動認識AI」の研究開発を2015年の創業から続けている。とくに人の骨格情報から動きを検知する技術は同社独自のものであり、直近でディープテックの国際コンペティションにて世界1位を受賞したほどだ。
巡回ロボットの搭載カメラに対応
スマートビルディングの基盤に
今後アジラは、防犯カメラだけでなく施設内を巡回する警備・清掃ロボットの搭載カメラにも対応する予定で、防犯カメラではカバーできない死角の補完を目指していく。また、人の動作に加え設備の音にも着目し、異音を検知した際に通知を出すシステムの開発を進めている。
将来的なビジョンとして、防犯カメラなどの設備から収集するデータと天候などの外部データを掛け合わせ、警備員の配置を自動判断したり空調やデジタルサイネージを自動制御したりするなど、スマートビルディング化を促す統合システムを目指す。また、大規模言語モデルと映像AI を統合する革新的な研究開発に着手し、ロボットとの連携を通じた施設管理のAI エージェント化を構想している。
最後に尾上氏は「当社のシステムは、高いコストパフォーマンスで不動産価値向上に寄与するものと考えている。早期に導入するほど、蓄積データの増加によりAI の学習機会が増えるため、より高い効果を発揮する」と結んでいる。

尾上剛氏
代表取締役CEO 兼 COO