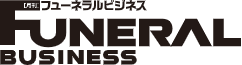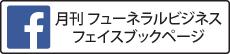『月刊フューネラルビジネス』
トップマネジメントセミナー2026
トップマネジメントセミナー2026

「ヒューマンリソースマネジメント元年」「事業再構築元年」
2026年、葬祭業界の針路
さらなる多死社会に向かうなか、今後は施行スタッフをはじめとする人材をいかに“採用”し、いかに“育成”するかが重要になります。同時に、生産年齢人口の減少期においては、“省力化”“省人化”などを実現する、「デジタル化」と「DX」改革が必須となります。また、人的資源を最大限に活用し、成果を上げるためには「戦略的人材マネジメント」が求められます。そして今後は適材適所の人員配置や高齢者雇用、さらには外国人労働者の活用などと、本格的に取り組まなければなりません。
「トップマネジメントセミナー2026」では、「ヒューマンリソースマネジメント元年」「事業再構築元年」なるテーマのもと、超高齢化・生産年齢人口減少期における、多死社会への本格対応に向けたヒントを探ってまいります。
参加申込み
開催終了
※「一般・定期購読の方」からお申し込みの場合は、システムの仕様上1回のお申込みにつき1名様までの受付となります。
複数名でのご参加をご希望の場合は、お手数ですが人数分のお申込みをお願いいたします。
◆セミナープログラム(10:30~16:50)
10:30~11:20 第1講座
テーマ講演【ビジネスモデル再構築】
2026年ビジネスモデル再構築元年
超高齢化・多死社会への本格対応
―― 経済産業省目標2029年度労働生産性24%UPを実現する
・ 2026年を「再構築元年」とする理由
・ 葬儀社にとっての危機とチャンス
・ 再構築の方向性(未来のビジネスモデル)
・ AI・自動化による業務の効率化と顧客対応の進化
・ 労働時間あたり付加価値をどう高めるか
・ 外国人労働者の雇用をどう考えるか?
・ 補助金・助成金を活用した経営強化
・ 医療・介護・行政と繋がることで、葬儀社が「終身サポート産業」

小泉 悟志
㈱エンディング総研、㈱コンサルティングファーム
代表取締役/中小企業診断士
こいずみ・さとし●1969年生まれ。銀行勤務後、ベンチャー企業の取締役を数社経験。㈱エポックジャパン(現㈱家族葬のファミーユ)取締役を退任後、葬儀業界専門コンサルタントとして独立。施行件数のアップ、プランの見直しによる施行単価の改善などによる売上げ拡大を強みとする。その支援先は10~50名規模が多く、また近年は、葬儀社のM&A支援も多数手がける。
11:30~12:20 第2講座
注目企業①【DX・SNS活用】
Web改革!
料金提示から実例開示へ
―― 「こういう葬儀がしたかった」に応える葬儀実例開示のポイント
・ 故人の遺志、遺族の想いをカタチにしてこそ葬儀の本質
──葬儀料金よりも葬儀内容の訴求が重要
・ SNS投稿
──専任スタッフをはじめとする、効果的な人員配置と遺族折衝のポイント
・ 葬儀社によるWeb活用・SNS展開が必要なわけ
・ 葬儀社にDXが求められる理由
──生産性向上、社員マネジメント、LINE相談など多様化・個別化への対応

中川 貴之
むすびす㈱ 代表取締役社長
なかがわ・たかゆき●1973年生まれ。98年ブライダルプロデュース会社の設立に参画し、2001年に株式上場を果たす。02年10月、㈱アーバンフューネスコーポレーションを設立。いち早く営業窓口としてのインターネット活用に取り組み、同社の年間施行のうち、80%が自社ホームページへの問合せからの受注である。07年ハイ・サービス日本300選第1回受賞企業。08年ドリームゲートアワード受賞。20年10月、会社名を「むすびす株式会社」に変更した。明海大学非常勤講師。
『月刊フューネラルビジネス』23年11月号より同社プロデュースの葬儀レポート「ヒトモノガタリ」を連載中。
古賀 瑞菜
むすびす㈱ 人財開発部 広報PR課
こが・みずな●1998年生まれ。2021年明治大学国際日本学部を卒業後、むすびす㈱に新卒入社。エンディングプランナーとして現場経験を積んだ後、23年よりSNSの企画・編集を担当し、運用を開始。約1年で総フォロワー10万人、総再生2億回を突破し、業界最大級のSNSアカウントへと成長させる。24年10月広報・PR課新設に伴い、現在は広報戦略の立案・推進を担い、企業ブランディングの強化に取り組んでいる。
12:20~13:00 昼食休憩
13:00~13:50 第3講座
注目企業② 【地域共生・人材活用】
“選ばれる”ための地域共生活動と
適材適所の人員配置
―― 人と地域に寄り添うことで地域貢献・ファンづくり
・ 地域密着、地域共生のための活動で地域住民との密接な関係を構築
・ カルチャー教室における地域住民からの講師登用
・ 事業多角化による効果的な異動・人員配置
──仏壇、ペット葬、遺品整理、デイサービス
・ 地域から選ばれるための人材育成
──葬祭ディレクター、全農認定
ゼネラル・シニアディレクター取得奨励

丹野 浩成
㈱JA東京中央セレモニーセンター
常勤監査役(前・代表取締役社長)
たんの・ひろあき●1996年、東京23区下南西部の6JAの広域合併により葬祭センター長。2000年10月、JA東京中央100%の出資を受けて「㈱JA東京中央セレモニーセンター」が設立され、初代代表取締役社長に就任。05年、全国JA葬祭で初のISO9001:2000を取得。06年より「世田谷区立区民斎場みどり会館」の指定管理者に認定される。07年全国JA葬祭研究会の初代会長に就任。モニターレディ制度や健康をテーマとした「輪っとふれあい健康フェスタ」など、地域共生を実践した各種イベントを推進。全国JA葬祭の先駆けとなり、研修先として受入れも行なう。10年よりJAグループ葬祭資格試験制度の導入に伴ない、試験委員のメンバーとして参画。個人情報保護法による「Pマーク」を取得(12年)。17年、世田谷区に介護保険利用施設「半日型リハビリデイサービス」を開始。ペット供養「ペットの天国」とメモリアルグッズ「ペットの空」のペット葬事業開始。同時に家屋の片づけ事業も開始する。19年、大田区に介護保険外利用施設「JA健康長寿俱楽部」を開設。21年11月に代表取締役社長を退任し常勤監査役で会長に就任。22年6月、18年に全農・農流研・研究会三者の合同組織となった「全国JA葬祭経営研究会」の初代会長職を退任(現理事)。「ペット火葬協会 東日本」 顧問(18年~)。
14:00~14:50 第4講座
注目企業③ 【人材育成・雇用】
これからの人材育成と雇用形態のあり方
―― “セレブ流” 20代女性が働きやすい環境整備と外国人雇用
・ セレブが目指す人材活用の根底にあるもの
・ 女性が活躍できる雰囲気づくり
──「妊活」→「産休・育休」→「再雇用」が生み出す好循環
・ 確実に減少する働き手! 業界に先駆けて外国人を雇用
・ 人材育成のキモとは

三須 榮光
㈱セレブ 代表取締役
みす・ひでみつ● 1975年生まれ。97年より大手互助会に8年在籍後、05年㈲Celebration Life(セレブレイションライフ)設立。10年に現社名である㈱セレブに商号変更。15年「ここだけの家族葬ホール」オープン。設立当初から低価格を売りにし、オリジナル葬にこだわり、千葉県船橋市が拠点でありながら、1都4県の広域で施行。心からの感動・感謝をモットーとし、葬儀の演出にこだわりファンづくりに特化。クチコミからの受注とリピータ率が高い。家族葬を売りにしているが社葬・合同葬も数多く手がける。21年には2号店「ここだけの家族葬ホールR」を開業。23年6月に設立されたYEG葬祭部会初代会長に就任後、この6月に2年の任期を終えて会長職を勇退(現在メンバー80人)。今後も業界発展のために奔走し続ける。
15:00~15:50 第5講座
注目企業④ 【組織マネジメント】
永続的な企業存続を目指した
人事考課評価のつくり方
―― 「見える化」することで納得できる人事考課とは
・ 葬儀社が陥りやすい人事考課表の落とし穴
──残業する社員は偉い?/年功序列は絶対的である?
・ トップダウンで決める人事評価から社員総意でつくりあげる人事評価へ
・ 成長支援・進捗確認・悩み相談
──信頼関係を築く高回転評価面談
・ 導入後、働き方はこう変わった!
自由な目標設定で主体的に動く組織文化変革

渡邊 安之
㈱花安 代表取締役
わたなべ・やすゆき●1984年、新潟県新発田市生まれ。大学在学中にカナダ留学を経験。卒業後、福島県内で高校教師を勤める。その後、新発田市内で家業である「花安新発田斎場」に入社。プレッシャーと苦難に耐える日々を過ごしたが、13年に「孤独死」と相対したことによって、これまでもっていた人生に対する価値観を大きく変えた。23年6月、代表取締役に就任し、現在は回りの人を巻き込みながら独自の地域戦略を描き、地域加盟店事業、樹木葬霊園、クラフトビール醸造所「TSUKIOKABREWERY」、空き家再生など複数の事業を立ち上げることに成功。人に任せる経営で多業種を展開し地域の需要を「面」で押さえる地域複合企業を目指す。売上高約2倍、式場数3倍、従業員数2倍、7年連続利益率改善、シェア率向上に貢献。MBA経営管理修士(専門職)修了。
16:00~16:50 第6講座
注目企業⑤ 【施設開発】
コンビニ改修型安置施設の新たなカタチ!
―― これからの時代に適応する新発想の“お見送り施設”モデルプラン
・ これまでの葬祭業界とこれからの葬祭業界(進む小規模・簡素化)
・ 従来型のコンビニ改修型会館のメリット・デメリット
・ 新発想の施設モデルプランの全容
──コンビニ改修でも遺体安置室(保冷庫8基)を完備した新お見送り施設
・ まとめ

岩本 元彦
㈱ハナブ商店 代表取締役
いわもと・もとひこ●1976年生まれ。99年よりハナブ商店で16年勤務後、2015年に事業承継をし、株式会社ハナブ商店を設立。15年の年間葬儀施行件数35件と廃業寸前の葬儀社から、24年には年間300件までに急伸。設立10年目の節目となる今年11月に、新たなお見送りの形としてコンビニを改修した、遺体安置をメインとしたお見送り施設「LAST REPOSEいばらき」をオープン。茨木市立斎場での市営葬儀をメインに10年先を見据えた火葬場の待ち状況を予想、遺体安置保冷庫を導入した長期預かりにも対応する新発想の施設として注目を集める。
16:50~ 終了・名刺交換(希望者)
※セミナープログラムおよび登壇者は、開催までに変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
開催概要
| 開催日時 | 2025年12月5日(金) 10:30~16:50 |
|---|---|
| 会場 | 都市センターホテル |
| 参加費 | 一般価格:69,300円(1名様につき)
●綜合ユニコムにて年間定期購読契約中のお客様
※「一般・定期購読の方」からお申し込みの場合は、システムの仕様上1回のお申込みにつき1名様までの受付となります。複数名でのご参加をご希望の場合は、お手数ですが人数分のお申込みをお願いいたします。 |
内容に関するお問合せ
綜合ユニコム株式会社
『月刊フューネラルビジネス』トップマネジメントセミナー事務局
TEL.03-3563-0043