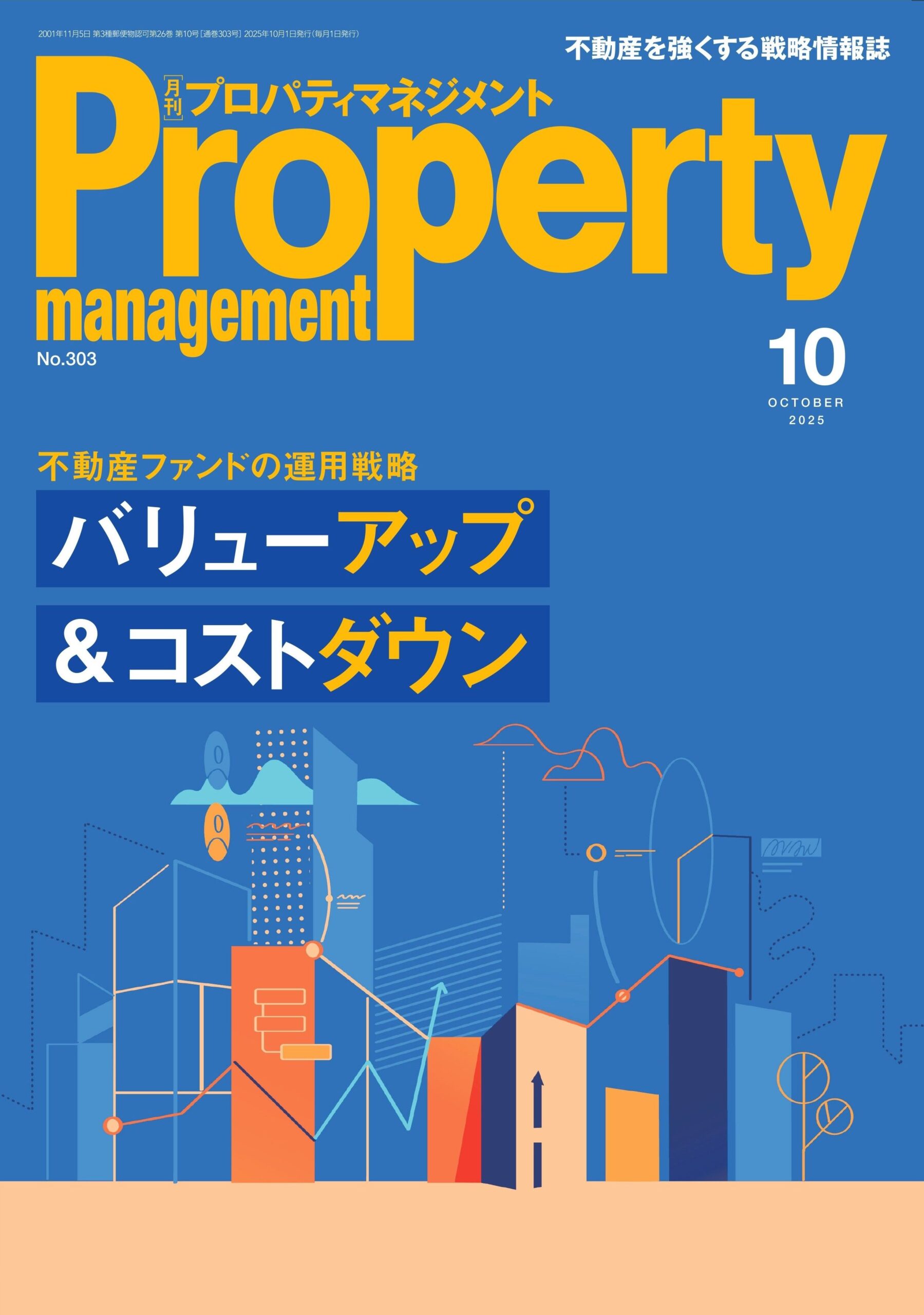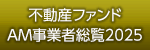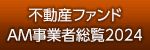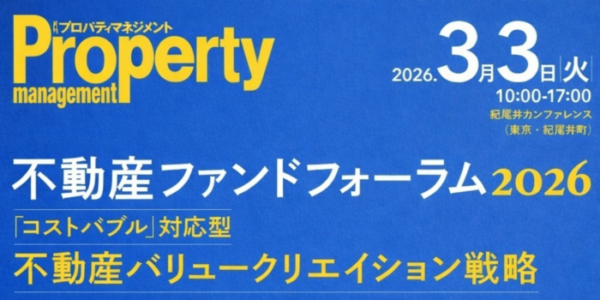――多幾宏平[マーケティングリアルティ]
コモディティ化からの脱却
【第1回】マーケティング視点の不動産投資講座
不動産投資は相場に依存した収益構造になりがちで、土地値、建築費、金利などの上昇が収益を圧迫する状況が続いています。
しかし、視点を変えると別の収益構造を見出すことができます。本連載ではマーケティングの視点から不動産を再設計し、ユーザーのニーズを起点にした新たな投資モデル構築のヒントをお届けします。
相場頼みの投資、どこまで通用するか
タイトルで記した不動産のコモディティ化とは、相場でしか貸し出せない、相場でしか売れない状態になることを指します。また、相場で貸し出し、相場で売ることを前提とした不動産事業モデル化ともいえます。
コモディティ化した不動産でリターンを高めたい場合、(収益の幅が決まっていることから)相場価格よりも「いかに安く仕入れられるか」が勝負です。しかし多くの競合他社が存在している中、安く仕入れられるルートを確保すること、連続して安く買い続けることは困難でしょう。
もし安く仕入れるのではなく、賃料を高く取れる方法が確立できたら、どうでしょうか? 収益の幅が伸びるのであれば、相場価格で仕入れたとしても必要なリターンを維持できるわけですから、仕入れの選択肢が増えます。
では、既に賃料相場が形成されている市場で、どうやって高い賃料を取ることができるでしょうか? その手段として、マーケティングの視点を持つことが必要です。つまり、ユーザーのニーズを起点にしたアプローチ方法です。
ニーズが違うのにどれも似たようなホテル
ホテルを例に説明したいと思います。読者の皆さんがよく目にする単身者向けのビジネスホテル。なぜか同じようなレイアウトやサービスであることが多いです。なぜなら多くの不動産・ホテル事業者が、周辺にあるルームの価格やサイズ、稼働率の相場ばかりをベースに事業計画を立て、物件を取得・開発するからです。これは冒頭で説明したコモディティ化に他なりません。
ホテルは画一化しても、その利用者の属性とニーズは様々です[図表]。観光客なのか、ビジネス客なのか。ビジネス客でも寝るだけのスペースを求めている客なのか、ホテルで仕事をしなければならない客なのか。1泊なのか連泊なのか。それによって、ホテルへのニーズは異なるはずです。
![[図表]ホテル利用者の属性とニーズ](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/d25a9f61b26f12894d196133390da3b4.jpg)
![[図表]ホテル利用者の属性とニーズ](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/d25a9f61b26f12894d196133390da3b4.jpg)
にもかかわらず供給されるものが同じであれば、ニーズのミスマッチが生じ、利用者が多かれ少なかれ我慢を強いられます。そうなると「安いから我慢できる」「この価格なら十分満足」といった心理状況になり、価格は必然的に相場へと収れんされていきます。コモディティ化と価格競争は、供給側が自ら創り出しているとも言えます。
ニーズを分類すると見えてくるもの
東京のホテルに1人で宿泊する人の市場調査をすれば、属性、予算、滞在期間、利用目的を理解することができます。単に1人客と括らず、セグメンテーション、簡単に言うとニーズをグループ分けし、それぞれの割合を出していきます。ホテルを運営している企業であれば各グループ単位のデータは当然保有していることでしょう。
さて、どのグループをターゲットに置くべきでしょうか? そのグループからどう収益を上げるのでしょうか?
地方や海外から東京に単身で出張に来るビジネスパーソン、中でも数泊し、寝るだけでなくホテル内で仕事もするグループをターゲットにするとします。国内外から東京に訪れるビジネスパーソンの市場規模は大きいため、対象を絞ったとしても、1社で取り切れる規模ではないでしょう。
一般的なビジネスホテルで仕事をしたことがある人は分かると思いますが、狭い机、弱い照明、長時間座りづらい椅子で作業するのは苦痛です。そのため、近くのスタバに行き作業する人が出てきます。とはいえスタバは営業時間が限られている上、周囲を気にせずオンライン会議を始めるような人達の天国とも言え、積極的に選びたいわけでもないはずです。すなわち、ターゲットの人々にとっては、ホテルにしても仕事場にしても適切なものがないことになります。
WORK×STAY(働けるホテル)で収益を跳ね上げる
続いて、潜在ニーズ(不満)へのアプローチ(解決)と床面積の有効活用を両立させる商品設計が必要となります。ここでは「WORK×STAY(働けるホテル)」をコンセプトに商品設計を考えてみましょう。
まずホテルの共用部の中に魅力的なワーキングスペースを作ります。おしゃれなホテルラウンジに見えるよう工夫し、デスクワークに最適な机や椅子、照明、さらにウェブ会議ブースやドリンクバーなど本格的なコワーキングオフィスに負けない設備を用意します。
ワーキングスペースに多くの面積を割いた分、客室は小さく設計します。机を撤去しサイドテーブルとドレッサーを兼用化、ケトルや冷蔵庫も撤去する一方、ベッドの上でくつろげる工夫(とてもリラックスができる雰囲気)を施します。つまり、客室から削った機能をワーキングラウンジに強化する形で移設、寝る(STAY&RELAX)ためのスペースとしての客室と仕事(WORK)のためのワーキングスペースという形で、役割を明確に分離します。

利用者から見ると、同じ建物内にある充実したワーキングスペースの利用権が付いた宿泊パッケージという他にない高い利便性が魅力に映ることで、相場を上回る価格を設定できる可能性が出てきます。また客室を小さくしているため、多くの客室数を確保することにもつながり、さらに収益性が上がります。そのほか連泊客を対象としているため、リネン交換やチェックイン・チェックアウトなどにかかる人件費も削減できます。
本格的な作り込みがさらなる収益化の機会を作る
収益性を上げるポイントはまだあります。ホテル利用者は日中外出していることが多く、ワーキングスペースはその時間帯に余裕が生じます。それを補うため、ワーキングスペースの利用権を外販して収益源を追加します。ホテル利用者と周辺ワーカーでは利用時間帯が異なることに着目したもので、ワーキングスペースの稼働率を高めることができます。
「WORK×STAY(働けるホテル)」を、東京に来る国内外のビジネスパーソン向けの新しいホテルコンセプトとしてブランド化し、横展開できる可能性は大いにあると思います。さらに、そのホテルに泊まることが「ちょっと所得の高いビジネスパーソンのステイタス」になるようなブランディングを最初から意図して作れば、時間の経過につれてより価格を上げていくこともできるでしょう。
今回は単身者向けのホテルを例に説明しましたが、マーケティングの視点はすべてのアセットタイプ、既存ビル再生/新規開発いずれにも応用できます。ユーザーのニーズを起点にして不動産投資を設計していくことが、コモディティ化から脱却する第一歩ではないでしょうか。