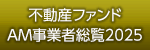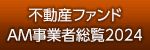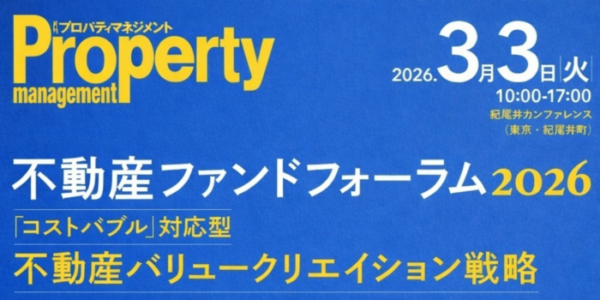――遠藤俊二郎氏[CBRE] に聞く
主戦場は生成AI×地方
適地選定5つのポイント
【試し読み】
データセンターは、いま国内不動産事業者が最も注目する資産クラス。
需要拡大は確実視され、投資対象としての魅力は非常に高い。
一方で、課題には参入ハードルの高さがある。投資妙味や事業参入の可能性、
成功の条件について、CBREの遠藤俊二郎氏が語った。
高まる需要量、348倍の試算も
不動産投資市場でデータセンターの開発・投資事業への関心は年々高まっている。クラウドサービスが台頭する以前は、システム開発会社が運営するデータセンターが主流だった。しかし2016年頃から、クラウドサービス提供者向けのハイパースケールデータセンター(HDC)の開発計画が急増。国内では三井不動産や三井物産系、海外勢では日本GLPやPAG系などが先行参入している。
HDCをはじめとするデータセンターは、大量の情報処理能力と高品質な通信環境が求められるため、東京・大阪近郊など大都市圏で集中的に開発されてきた。ただし、施設の運営ノウハウや、用地・電力の確保といった条件が必要であり、参入障壁は極めて高いのが現状だ。
地方×生成AI向けを国も後押し
立地選定5つのポイント
2022年頃からは、クラウドサービスに加え、生成AIサービスの普及なども相まってデータセンター投資・開発に拍車がかかった。今後、需要拡大が確実視されるのは、この「生成AI向けデータセンター」である。これまでの開設事例は首都圏、関西圏に集中していたが、今後その主戦場は地方に移る見通しである。生成AIの学習用途ではレイテンシー(通信遅延)に対する許容度が高く、地方立地でも十分に機能するためだ。
日本政府も後押しに動く。再生可能エネルギーなどの電力インフラと情報通信インフラを一体整備し、電力需給ひっ迫の緩和と地方分散を進める「ワット・ビット連携」を推進中である。施設整備には補助金活用も可能であり、地方立地の魅力を高めている。新築だけでなく、既存施設をGPUサーバーを安定的に稼働させられる生成AIの運用に対応した施設へ改装する動きも増加している。
地方における生成AI向けデータセンターの適地を選ぶ際の主な判断基準は、①再生可能エネルギーの発電ポテンシャル、②電力コスト、③インフラの整備状況、④工場など生産拠点の集積度、⑤地震の発生確率の5点である[図表]。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
再生可能エネルギーの発電ポテンシャル |
再生可能エネルギーの潜在的な発電量を試算する上で重要な指標は、土地などの設置可能面積、風速、河川流量などの資源量である。太陽光、陸上風力、中小水力、地熱を合計した再生可能エネルギーの導入ポテンシャルでは、北海道が突出して高く、岩手・青森などの東北地方が続く。広大で平坦な土地が多く、年間を通じて安定した日照や風量が確保できることが背景にある。 |
電力コスト |
特別高圧受電の全国平均販売単価では、原発稼働のある九州が最安。一方で北海道は最も高く、九州の約1.5倍(2025年2月時点)に達する。ただし冷涼地では外気冷却の活用により使用電力量を削減できる。国は2029年以降に新設される施設に対し、電力使用効率(PUE)1.3以下を求める方針であり、電気料金単価だけでなく、冷涼な気候がもたらす省エネ効果も立地選定において重要となる。 |
インフラの整備状況 |
通信用光ファイバーなどは道路や電柱、下水道の管路を経由してデータセンターに引き込まれる。また、洪水・高潮・土砂災害など自然災害リスクの低減に寄与する堤防・護岸・ダムなどの整備状況もデータセンターの立地選定において重要となる。これら社会資本ストックの残存価値は、東北地方や中四国地方の一部、和歌山、九州地方で高く、東京や大阪など大都市では比較的低い傾向が見られる。 |
工場など生産拠点の集積度 |
鉄鋼、化学、電子部品・デバイスなどの工場が集積する地域は、AIデータセンターの運営に必要となる大量の電力・水が予め引き込まれていることが多く、データセンターへの転用において優位性が高い。とくに愛知、兵庫、福岡では鉄鋼系が、三重、山形、北海道では電子部品系工場の除却・売却が多く有望である。 |
地震の発生確率 |
日本は地震多発国であり、地震の発生確率の低さと立地選定は密接に関係する。今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率が低い県庁所在地は、札幌のほか、東北や日本海側の都市に多い。こうした地域は、被災した他地域のデータセンターを補完するバックアップ拠点としても有効である。 |
それぞれみていくと、①再生可能エネルギーの発電ポテンシャルは、北海道が突出して高く、岩手・青森などの東北地方が続く。②電力コストは、……(中略)
コンバージョンなら1年以内で事業化も
データセンターは拡大途上の市場であり、案件化にあたっては、まずオペレーターや事業者のニーズを把握し、そのうえで前述のポイントを押さえて適地を探すのが基本だ。
一方、黎明期ゆえ、需要を見込み先行して用地を確保し、開発計画を立てるリスクテイク型投資も有効である。北海道・石狩市で開発中の「石狩再エネデータセンター第1号」がその好例である。
新規開発ではゼネコンとの交渉に約1年、着工から竣工まで約5年を要する。このため、長期資金を持つ開発ファンドやオンバランス投資が可能な事業会社が主なプレーヤーとなる。
一方、短期事業化を狙うなら、既存工場のデータセンター転用という選択肢もある。KDDIが2025年4月に取得した「シャープ堺工場」は、年内稼働予定であり、1年未満で事業化まで漕ぎつけるなどスピード感を示している。
(続きは本誌で)
遠藤俊二郎氏

Head of Data Centre, Capital Markets, Asia Pacific