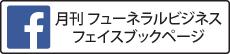――岡崎仁美氏 家族葬のファミーユ 代表取締役社長
「生活者目線ですべてを見直す」
現場が主役の進化共創経営が強み
[特集]事業展望2026 ――注目の経営者に聞く
2026年1月号特集「事業展望2026――注目の経営者に聞く」では、業界注目の経営者に8人にご登場いただき、社長就任の経緯から経営方針・戦略、および2026年以降の取組みなどについて伺った。Web版では、24年6月に㈱家族葬のファミーユの代表取締役社長に就任した岡崎仁美氏のインタビューを掲載する。

岡崎仁美氏
家族葬のファミーユ 代表取締役社長
おかざき ひとみ●大学卒業後、人材派遣、販促メディア、人材メディア、ITソリューションなどを提供する㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)に入社。主に人材メ
ディア領域に従事し、就職サイト「リクナビ」の編集長を長きにわたって務める。同社退職後、一般企業での事業運営に携わったのち、2019年3月、取締役として㈱家族葬のファミーユに参画。リクルート時代に培ったノウハウを活かし、ボードメンバーとして事業成長を牽引し、24年6月、同社代表取締役社長に就任。同社の持株会社である㈱きずなホールディングスの取締役兼CSOも兼任する。
「選択肢のある豊かな社会」を目指す点に
共通項を見出し、未知の葬祭業に転身
――岡崎社長は異業種からの転身とのことですが。
岡崎 大学卒業後、リクルートに入社したのですが、当時のリクルートには、“定年まで勤め上げるよりもここで学んだことを活かして社会貢献” といった価値観があり、そこへの共感が入社動機でしたので、いずれは別の業界で、と自然に考えていました。実際には、30歳代後半で3人の子どもの出産があり、自分としては予定よりもやや長い25年の勤務ののちに退社を決意。仕事人として憧れの先輩からの声がけで9か月ほど別の会社に籍を置きましたが、別の会社に転じてみて、自身が仕事を通じて実現したいことがいっそう浮き彫りになり、次の道を再度模索することにしました。そうしたとき、リクルート時代の上席の1人で、きずなホールディングスの代表として先んじて葬祭業界に転じていた中道から「この業界を真っ白にしたい」という希望を聞く機会があり、直感的に強い共感を覚えて参画することにしたのです。
――葬祭業界への転身に不安はありませんでしたか。
岡崎 もちろん、私のような新参者が受け入れられるのかという不安はありました。一方で、当社は「お葬式を家族のものに。」というコンセプトのもと、「葬儀社目線を一切否定し、生活者目線ですべてを見直す」方針で運営していましたので、であれば「門外漢だからこその貢献ができるのでは?」とも思いました。もちろん事前に現場見学もさせてもらいました。日々お客様に寄り添っているスタッフの人たちに直接話を聞くなかで、「まったく違う業界だけれど、自身がこれまで培ってきたことは、ここでも役に立てるかもしれない」と思えたことが、決断を後押ししました。
――といいますと……。
岡崎 リクルート時代、私は「リクナビ」の編集長を長年務めるなど、主に採用領域での仕事に従事し、採用市場を長きにわたって俯瞰してきました。昨今、ありとあらゆる業界で人材不足が叫ばれていますが、葬祭業は就職難の時代においてもどちらかというと不人気業種でした。これはサービス産業全般に共通する課題ですが、労働環境や賃金水準が製造業などと比べて見劣りし、いわゆるステータスが高いとは言い難い。とりわけ葬祭業はその傾向が強く、顧客価値を創造する主軸であるはずの「人」がネックになっています。
一方の求職者にも、たとえば集団を統率して先頭に立って難問をクリアするといったことには興味が湧かないが、目の前の人のちょっとした心の動きをいち早く察知し、そっと寄り添ったり優しく支えたりするのは得意という人が数多くいらっしゃいます。それぞれに個性があり、合う、合わないも異なるはずです。それなのに就職活動となると、学生はいっせいにみんなが知っていて初任給も高い有名企業から順番に受けたがる。このすれ違いの構造は、双方にとって大きな損失を生んでおり、人材領域に長く携わった私自身の問題意識にもなっていました。自身が葬祭業界に飛び込み、より主体的にミスマッチ解消に取り組めば、会社や業界にも貢献できる。これまでの経験が役に立つのであれば、自身の充実にもつながると思ったのです。
――求職者と企業、双方の立場に立った組織マネジメントの面で力になれると思われたわけですね。
岡崎 新卒者の場合、限られた期間のなかで就職先を決めることになります。葬儀はさらに短い期間のなかで葬儀社選びや諸々の手続きを行ないますが、双方に共通するのは「情報の非対称性」です。就職もお葬式も、主体者としての経験は人生に1~2回程度の人がほとんどですよね。言い換えれば、人生のなかで経験頻度が少ないがゆえに、「何をどう考えればいいのか」といった、不安や不明などの「不」がまだまだ多く存在する領域といえるでしょう。そうした点から、就職と葬儀には意外と共通項がありそうだと感じましたし、いま思えば、未知なる業界だったからこそ、強く興味を惹かれたように思います。
ボードメンバーとして参画し
マネジメントと業界の地位向上に奔走

――入社されたのはいつのことでしたか。
岡崎 19年3月に取締役として迎え入れていただき、最初はマーケティングから、そこから徐々に担当領域を広げていきました。現場の支社長も経験するなかで、お客様の求めているものや、従業員全員が提供している価値、同業他社との違いなどをより具体的につかんでいったように思います。
さまざまな業種の出身者が集う家族葬のファミーユ(写真は同社取締役と支店管理職)
――業務を推進するうえで、むずかしいと思われたことは。
岡崎 これはサービス産業全般にも共通することなのでしょうが、いちばん当惑したのは「会議設定がむずかしい」ことです(笑)。たとえば、マネジメント研修を実施しましょう、と意思決定しても、その開催に向けたスケジューリングが一苦労。24時間365日顧客対応が生じる葬祭業において、みんなで集まって研修や会議を行なうときのハードルの高さは、業界ならではの課題なのかもしれません。しかし、それを嘆いていては話になりません。そうした前提のなかでも、いかに経営の意思決定を現場に伝達し、現場が顧客から得たことを経営の意思決定に反映させるか、ここが工夫のしどころだと考え、いまも最優先で取り組んでいます。当社は「家族葬のパイオニア」ですが、私が当社に参画した頃はまだ家族葬は傍流で、葬儀といえば一般葬でした。ところが、コロナ禍を経て家族葬と一般葬のポジションが逆転します。大きな意識改革が必要だと危機感を覚えました。
――何をきっかけに意識改革をされたのですか。
岡崎 当社の持株会社であるきずなホールディングスは、20年3月、まさにコロナ禍に突入したその時、東証マザーズ(当時)に上場を果たしました。ちょうどその頃から、「家族葬」が葬儀のメインストリームに躍り出たわけです。当時、上場という1つの区切り、新しいステージがはじまるタイミングでしたので、新たな「10年ビジョン」を掲げました。いま振り返れば、外部環境・内部環境双方が大きく変化する節目の時期だったのでしょう。
――岡崎社長がその中心的存在だったのでしょうか。
岡崎 もちろんボードメンバーの1人として主体的に関わりましたが、けっして私だけというわけではありません。当社は執行役員も含め、多様な人材が集っています。それぞれのバックグラウンドや価値観と、みなで一丸となって目指す未来を融合させるように対話を重ねてきたと思います。
――とはいえ、貴社の事業規模からすれば、苦労される点が多かったのでは。
岡崎 おっしゃるとおり、店舗数がふえるにつれて、あうんの呼吸だけでは成り立たなくなります。当社は「葬祭業はローカルビジネス」であると捉え、地域ごとに最適化した運営を優先していましたが、各地域の組織サイズも大きくなり、より体系的に動く必要が顕在化したのです。
――そのとき、どのような対策を講じられたのですか。
岡崎 ひと言でいえば「マネジメントの標準化」です。統一したマネジメント研修を全マネジャーが受講することで、マネジメントに関する「共通言語」をもつよう努めました。当社は他社からの転職組が大半で、被マネジメント経験もマネジメント経験もすべてともに体験してきたような会社とは文化が違います。マネジメントの要諦とは、どんな会社でも変わらないのかもしれませんが、それを指す「言葉」が違うと理解不足が起きてしまう。これだけ家族葬もコモディティ化してきましたから、異なる個性や動機をもつ多様な人々を共通の目標に向かって導き調整する力、つまりマネジメント力が他社との差をつくることは間違いありません。
現代は不確実性の高い時代といわれます。この常に変化する時代のなかで、個人の成長と組織の成功を同時に達成するという現代のマネジメントのむずかしさが、肝心のマネジメント層に負担がかかりすぎないようにするには、マネジメント層の全員が「同じものを見て、チームで戦う」ことが不可欠だと考えたのです。
――現場スタッフとのコミュニケーションを図るなかで、業界のイメージは変わりましたか。
岡崎 いちばん驚いたのは、「年齢・性別問わず、何と優しい人ばかりなんだろう!」ということです。採用領域の仕事に長く従事していましたので、業界や企業規模による人材タイプの違いはそれなりに把握しているつもりでしたが、想像以上でした。葬祭業はどの職種も容易な仕事ではありません。約2万種あるとされる仕事のなかから、わざわざ選び、継続している人たちに心から深いリスペクトを覚えました。そうした姿を見たとき、あらためて「業界の地位を上げていかなければならない」と決心しました。
――一方で、優しい人ばかりでは企業は成り立たないことも事実です。
岡崎 確かに、以前はマネジメント研修を設定しても、「ご依頼が入ったので研修には参加できなくなりました」と欠席する人が少なくありませんでした。「目の前のお客様を放っておけない」という価値観も尊重しつつ、「管理職自ら出動するのではなく、メンバーに思い切って任せてみて、自身はより長い時間軸での顧客貢献を優先してほしい」と期待を伝えることで、少しずつ理解が浸透したように思います。
――社長就任後に取り組まれたこととしてあげられるのは何でしょうか。
岡崎 コロナ禍もあり、この5年ほどは本当に激動の期間でした。振り返れば、いろいろと新たな取組みがありました。それらはいずれも私個人ではなくみなで進めたことですが、私が社長に就任する前の支社長や副社長の頃から意識的に注力してきたのは、人材登用です。特にパート社員の活躍推進について強く旗を振ってきました。葬祭業は顧客サービス業ですから、変革の萌芽は、常に顧客との最前線に宿るはずです。いざ葬儀のご依頼をいただいた際は、正社員を中心とした葬祭ディレクターが主導します。しかし、当社はお葬儀のないときも会館をオープンし、予約がなくてもいつでも事前相談に対応する「事前来館」に注力しており、そこを担うスタッフの多くはパート社員です。このパート社員のみなさんこそが、私にとって貴重な先生、情報源です。まだお客様になる前の生活者のみなさんと接し、フラットな意見にふれ、これまたフラットにフィードバックしてくれる。なかにはその活動を通じて「もっとこうしたい」「こう改善すべき」という強い問題意識をもつ方もいらっしゃいます。そうした方には、もちろん状況が許せばですが、「もっと活躍の場を広げてみませんか?」とスカウトしています。
この業界は女性経営者も少なくないですが、当社では私より以前に女性役員はいなかったようです。もし私の存在が女性役員や管理職を身近なものにし、「私もやってみたい!」と思う人が1人でもふえてくれれば、当社の多様性をより高める一助になるかも知れません。そうであればうれしいですね。
――そのためには、管理職を含めた人材育成・教育が重要です。
岡崎 コロナ禍による葬儀の小規模化は、家族葬を主とする当社にとって追い風となりましたが、一方で人員数の確保や教育など、けっして完璧に追いついているとはいえません。経営者として、人(社員)を預かっている以上、「ここに集う1人ひとりが成長する機会を提供することが私の責務である」と考えています。そうでなければ企業成長もあり得ない。だからこそ、目の前のことにただ対応するのではなく、ありたい未来に向けた布石をみなで打っていけるような、強いマネジメントチームをつくり上げたいと思います。
「家族葬」へのこだわりと
「顧客満足」を超えた「顧客推奨」運営

――会館運営についてはいかがですか。
岡崎 当社の強みは、何といっても「家族葬」へのこだわりです。ただ、私どもが標榜する家族葬は“家族のためのお葬式を提供する” ことであり、小規模・簡素化した葬儀を単純に推奨するものとは一線を画しています。根底にあるのは、葬儀とは、ご家族のみなさんがそのご縁を紡ぎ直すためにあるという思想です。「葬儀」というモノではなく、「葬儀を通じた顧客価値」を提供することにこだわりをもっているのがいちばんの強みだと思います。
「家族葬のファミーユ 帯山ホール」(熊本市中央区)
そのこだわりの実践度を測る指標として、当社ではNPS®(Net Promoter Score®、顧客推奨度)※を中心に据えた運営を行なっています。おかげさまで、「ほかの人にもお勧めしたいですか」という項目については、95%以上の方が10段階中7点以上の評価を下されておりますので、当社の家族葬への思いがお客様にも一定以上伝わっているのではないかと思います。
※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPSはベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクベルト、NICE Systems,Inc.の登録商標です。
――現状の市場環境についてはどのようにお考えですか。
岡崎 ポストコロナが定着するなか、大勢の人をお招きする葬儀も心置きなく営まれている認識です。その一方で、たとえば2人だけでお見送りしたいというケースもふえている。お見送りする側・される側双方の年齢が高くなるにつれ、この傾向は徐々に高まっていくのでしょう。社会が変化すれば、当然、葬送慣習も変わっていくのです。
また、重要なステークホルダーである生花店や仕出し料理店などのパートナー企業の持続可能性についても、主体的に捉えていかなければなりません。たとえば、昨今の働き方改革によるドライバー不足などはわれわれの業界にとっても対処すべき課題です。地域によっては、病院なども含めた関係者が話し合って、夜間搬送の廃止を検討する動きなどもあると聞きます。
――今後の展開などについてお聞かせください。
岡崎 目前の競合は熾烈を極めながらも、業界の未来を見据え、垣根を越えた共存共栄の道を模索する。そんな時代がわれわれの業界にも訪れていると実感しています。そうしたなかで、当社は今後も燦ホールディングスグループの一員として、より質の高いサービスを、より多くの地域の皆様にお届けしてまいります。
――本日はありがとうございました。
本誌では岡崎氏のほかにも、注目の経営者計8人へのインタビュー記事を掲載しています。