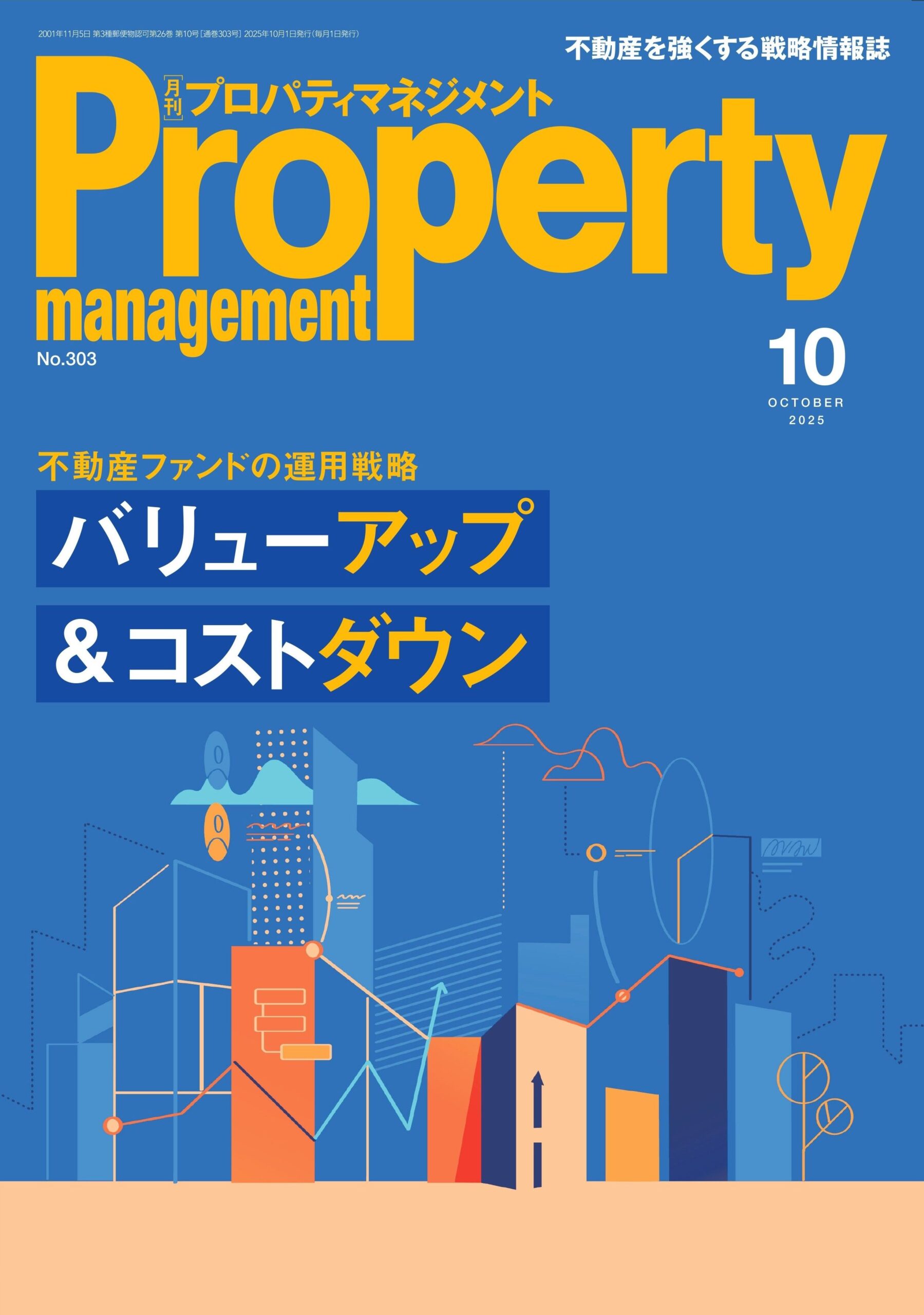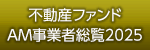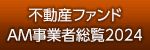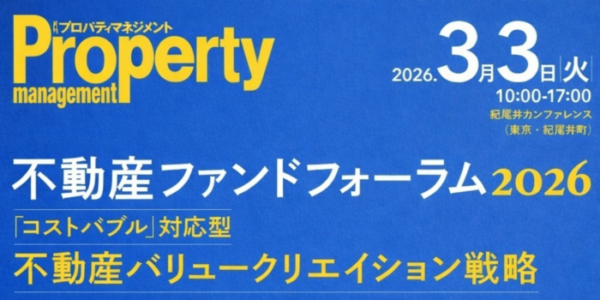――ADDReC
新ホテルブランド「Sumu」がつくる
この先の「暮らし」「住まい」のカタチ
【試し読み】
不動産コンサル・空間プロデュースを手がけるデザインファームADDReC(アドレック)は、Airbnbのビジョンとネットワークを活かし、新ブランド「Sumu powered by Airbnb Partners(スム)」を立ち上げた。
アパートメントホテルを基盤に、不動産(ハード)とサービス・コンテンツ(ソフト)を融合させ、強固な収益基盤を備えた次世代型宿泊事業を目指す。経年による不動産価値の向上を促す“ 増加蓄積型”の開発手法を採り入れた点も特徴である。
本稿では、そのビジネスモデルと活用のヒントを紹介する。
需要と供給のギャップ埋める新モデル
相見積もりで最適な事業者選定
Sumuは、旅行者の宿泊需要と供給側デベロッパーの事業課題の双方に応えるべく誕生したアパートメントホテルの新業態である。
宿泊需要では、海外の若年層(Z世代・α世代)の伸びに着目。彼らは観光だけでなく地域文化やコミュニティとの交流を重視し、「旅と生活の境界が曖昧で、暮らすように滞在できる施設を求めている」(ADDReC CEO・福島大我氏)。
一方、供給側の事業課題では採算性の確保にフォーカス。「地代や建築費、人件費が高騰するなか、デベロッパーは何よりも事業効率性を求めている」(同氏)。

双方要望に応える宿泊施設業態のひとつとして、現在アパートメントホテルの開発供給が活発化しているが、その中身をみると、継続性のある事業モデルとしては不完全といえる。多人数宿泊に対応した建物開発と機能配置に目が行く余りに、「中長期滞在者のためのサービスやコンテンツがおざなりで十分整備されていないのが実態」(同氏)。いわゆるソフト・オペレーション面において、需要に対し供給が追い付いていない状況だ。理由として、ホスピタリティや地域貢献といった価値は利害が一致しづらいこと、デベロッパー単体の能力だけで対処するのはむずかしい点が挙げられる。
「Sumuはまさに、それらの課題解決として立ち上げられた仕組み」(同氏)。
不動産+動産で価値向上
投資の入口から出口まで出番あり
Sumuの課題解決の特徴は、オープンイノベーションを活用し、事業パートナーの層を厚くした点にある。具体的には、宿泊予約プラットフォームAirbnbと連携し、ホテル・民泊運営会社、システムベンダー、FFE事業者、デベロッパー、メディアなど約200社が参加する「Airbnb Partners」のネットワークを基盤に、異業種協業による、宿泊者とデベロッパーの利害が一致したサービスを企画・実行する仕組みを整備した。「ホテル事業を通じた地域活性化を目指すデベロッパー、とくに鉄道会社の参画をおすすめしたい」(福島氏)。
ビジネスモデルの全体像は[図表]のとおり。施設開発では、投資家オーナーが土地・建物を保有し、ADDReCが建物デザインを監修。運営は、アパートメントホテルやビジネスホテル、戸建てホテルなどで50棟超の実績を持つ協業パートナーのカソクが担う。
![[図表]Sumuのビジネスモデル](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/addrec.jpg)
![[図表]Sumuのビジネスモデル](https://www.sogo-unicom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/addrec.jpg)
さらに、客室販売以外で収益を得る仕組みとして、Airbnb Partners加盟企業やホテル立地エリアの地元企業と連携し、「宿泊×メディア・コンサル・テックの展開を図る」(福島氏)。具体例としては、客室家具やアメニティのD2C販売、宿泊者分析データの提供、自治体向けの地方創生・防災支援コンサルティングなど。これらによりブランディングやコミュニティの形成を進め、宿泊事業に依存しない多様な収益チャネルを設け、安定的な収益基盤を築く狙いだ。
施設の開発・マーケティング・運営、さらに自治体・地元企業・住民との協業をトータルに監修するのはSumu事務局である。事務局はブランド管理会社Sumuが担い、オーナーへのブランドライセンス供与や開発監修料を収益源とする。「デベロッパー、設計企画、ゼネコン、ファンド、地権者、Airbnb Partnersや運営会社など、関係者全体を調整する司令塔の役割を果たす」(福島氏)。
旅行者と地域住民の交流ハブ目指す
Sumuが想定する建物規模は、1棟あたり15~60室程度。運営においては、不動産オーナーとカソクが個別に賃貸借契約を結ぶ形をとる。「賃料形態は、固定、固定+変動(割合はさまざま)、完全変動と、ファイナンス条件や建物所有者の方針によって提案する」(カソク代表取締役社長・新井恵介氏)。
館内機能はフロント、ラウンジ、カフェ、コワーキングスペースを基本装備とする。カフェは地域飲食店やクリエイターと連携、ラウンジは蔦屋書店を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が書籍・家電・アートをキュレーションする。「宿泊の場にとどまらず、旅行者と地元住民をつなぐ交流拠点としたい。地域の魅力を体験できるハブとして機能させる」(新井氏)。
5年・30棟開発で国内シェア10%獲得
Sumuは、「STANDARD(主要都市型)」、「LOCAL(地方リノベ型)」、「SMALL(個人所有物件リノベ型)」(すべて仮称)の3ラインを軸に、2030年までに30棟の開発を目指す。すでに東京都台東区などで4棟を進行中。第1弾は2025年12月、東上野にリノベーション型物件を開業予定だ。
開発は大手ハウスメーカー、デベロッパー、不動産ファンドと連携し、中長期的な開発・運営基盤を築く。新築でのファンドとの取り組み第1号物件は、昭和リースが組成するファンドが購入。カソクがストラクチャー管理から運営まで一貫して担い、安定した事業運営を図る。
パイプラインは東京・大阪・福岡を中心に展開中だが、将来的には海外都市へのアウトバウンド展開も視野に入れる。案件獲得ルートは地主やビルダーからの持ち込みに加え、デベロッパーとの協業も想定。「不動産でソーシャルインパクトを起こすことを目指し、財閥系をはじめ大手デベロッパーやCRE活用を模索する老舗企業とも積極的にタイアップしたい」(福島氏)。
日本政府が掲げる「2030年訪日客6,000万人」の目標に向け、滞在型宿泊の需要は今後さらに拡大が見込まれる。Sumuは、この需要と供給のギャップを埋めつつ、地域社会の活性化と観光産業の進化を同時に実現する新モデルとして、投資家やデベロッパーから注目を集めている。「将来的にはアパートメントホテル市場で10%のシェア獲得を目指し、オペレーターのFC展開も検討した
い」と福島氏、新井氏は意気込みを話した。