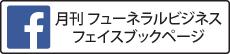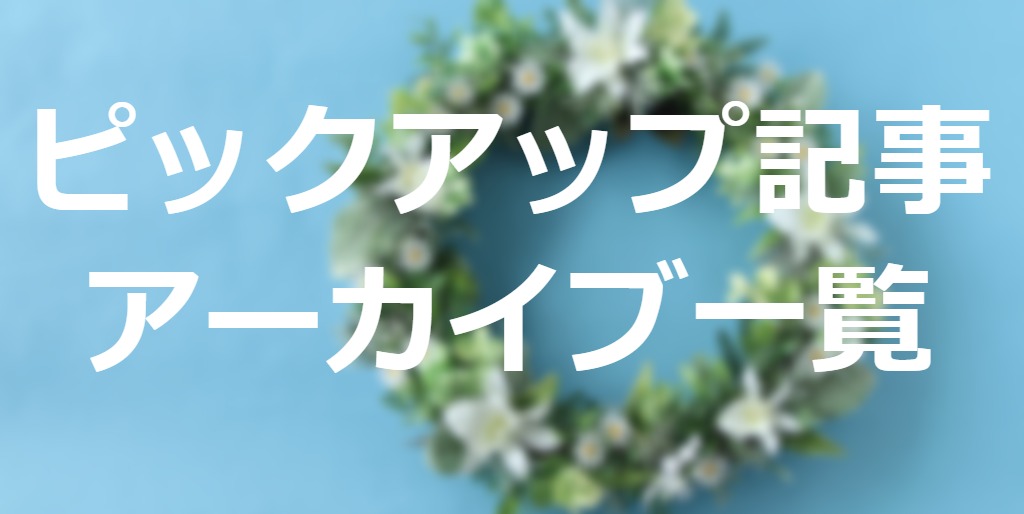── SunVillage[埼玉県北本市]
大型葬の祭壇で高品質をアピール
技術の継承目指し養成機関設立へ
[特集]生花演出 次の一手|ケーススタディ
社葬・お別れ会など大型葬の祭壇を数多く手がけている㈱SunVillage(サンヴィラージュ)。埼玉県の県央部に位置する北本市で、1963年に店売りの生花店として創業。その後、現在三代目を担う三村晴一氏が生花祭壇設営に舵を切った。三村社長に昨今の祭壇の状況、そして構想中の技術者養成機関について伺った。


栃木県での一般葬祭壇。間口3間、事前制作2人で4時間、現地設営2人で1時間
町の花屋さんから
生花祭壇の制作に業態転換
同社は三村社長の祖父が「三村花店」を興したのがはじまり。その後、三村社長の父が㈲ミムラ花店として法人化したのが90年。いわゆる“町のお花屋さん”であった。当時から葬儀社と取引関係はあったが、供花のみの受注で生花祭壇は手がけていなかった。そこで生花祭壇を扱えば周辺の生花店とは異なる路線で勝負ができると、三代目を担う三村晴一氏は生花祭壇事業者に修業に出る。2007年、修業を終えた晴一氏が家業に入るとともに社名・組織を㈱SunVillageに変更・改組し、代表取締役に就任した。SunVillageとして生花祭壇に注力していくことを標榜したものの、すぐに受注があるわけではない。そこで、生花業者や葬祭事業者に生花祭壇の技術を伝えるDVDと写真集を自費制作。09〜11年にかけて毎年DVDをリリース、トータルで500本近くを販売することができたという。「DVDや写真集は、手元に置いていつでも見ていただくことができます。見ていただく頻度が高まれば、営業をしなくても自然と認知度が上がるようになります。したがって、広告費以上の効果があるだろうと思いました」と、DVDと写真集の発売経緯を語る。
実際、DVDを見た事業者の反響を呼び、少しずつ生花祭壇の受注がふえ、現在では約30社から生花祭壇を受注するまでになった(ほかに供花のみの受注もある)。商圏は片道30分から1時間圏内。そのうち、約10社からコンスタントに受注しているものの、比較的低単価の祭壇が多い。一方、残りの約20社からは月1件ほどの受注だが、高単価の祭壇がほとんどである。平均すると、祭壇1件当たり18万円だ(コロナ禍後)。現在、設営件数は年間約800件に及び、そのうち約750件が一般葬・家族葬、約50件が社葬・お別れ会などの大型葬だ。三村社長を含め10人のスタッフ(パート含む)でこの件数を切り盛りしているが、昨今の働き方改革もあって、極力スタッフが残業をしないよう配慮している。「会社を大きくすることは考えておりません。まずはスタッフの生活水準を上げることを考えています。そのためには、当社の特徴である高単価の社葬・お別れ会の受注に注力しております」と三村社長。
平均すると1日約2件の生花祭壇を受注していることになるが、「単価にして3万〜4万円ほどの小さな仕事(祭壇)では、当社の特色を出すことができません。そのため、小さな仕事を10件やるよりは、ある程度単価の高い大きな仕事(たとえば30万円)を1件請けたほうがいいと思っております」と三村社長。小さな祭壇を数多く受注すると、スタッフに残
業を強いることになる。そのわりに売上げ、利益が低いとなれば、スタッフへの還元も薄くなる。それよりは、数は少なくともある程度の金額の祭壇を受注していけば、仕事にも余裕ができ、残業を強いることもなくなるという考え方だ。


(左)技術支援として関わった鹿児島県での社葬祭壇。間口5間、現地設営3人で8時間
(右)SunVillage制作の供花例
大型葬の依頼は岩手から兵庫まで
高い技術力で著名人の祭壇も多数担当
「お陰様で大型葬の依頼は年間約50件あります。それ以外に他社が請け負った大型葬の祭壇に技術支援として関わることがあり、それが30件ほどございます」と三村社長。自社で受注した大型葬は、自前のトラックで北は岩手県から西は名古屋あたりまで出向く。過去には兵庫県から依頼を受けたこともあるという。技術支援のケースでは、さらに広範にわたる。花材は現地の生花業者が用意するため、三村社長が単身で現地に向かえるからだ。
同社が関わった主な著名人の大型葬としては、元プロ野球中日ドラゴンズのエースとして活躍し、現役引退後は中日、阪神タイガース、東北楽天ゴールデンイーグルスで監督を務めた星野仙一氏のお別れ会(2018年)、元内閣総理大臣中曽根康弘氏の内閣・自民党合同葬儀(20年)、元内閣総理大臣安倍晋三氏の国葬儀(22年)など。政財界、芸能・スポーツ・文化人などの大型葬を多数手がけているのは、同社の技術力の高さを裏づけるとともに、最大のPRの場にもなっている。「当社の社名を訴求することはもちろんですが、三村個人の名前を売ることも考えています。生産者名を明記した農産物があるように、“三村がつくった祭壇”をアピールしてもいいのではないか。これは私だけでなく、ほかのスタッフであっても個人名を打ち出し、そのうち指名されるようになればいいですね」。高い技術力をもつ三村社長ならではの発想は、スタッフに名前を売れるレベルの技術者になってほしいという願いでもある。
三村社長は、技術講習にも力を注ぐ。07年からフローリスト養成校のJFTD学園日本フラワーカレッジ(東京都品川区)において、非常勤講師として生花祭壇の授業を担当。また、花キューピットの派遣講師として、全国各地で講習を担当したこともある。このほか、大手互助会やJAから依頼されて講習にも赴く。フューネラルビジネスフェアでは設営のデモンストレーションを幾度となく行なっているほか、海外においても中国の葬儀展示会でデモンストレーションを行なった。
低価格葬主流に危機感
技術者養成機関の設立を構想
三村社長によれば、コロナ禍を経て家族葬は洋花でボリュームを出し、使用本数を抑えたアレンジが多くなったという。その一方で、1間幅の祭壇でも白ギクの祭壇へのニーズは高い。いまなお大型葬の祭壇は白ギク中心の整然とした祭壇が多いという。白ギクの祭壇は高い技術力が必要で、大型葬は亡くなった方の功績を讃えるのが趣旨でもあることから、故人の功績に見合う高い技術力を要する白ギクの祭壇が多いのではないかとみている。
そうしたなか、同社では白ギクを繁忙期には常時5,000本、閑散期でも3,000本をストックし、白ギク祭壇の設営依頼に備えている。「祭壇設営の依頼をいただいている葬儀社さんは、このコロナ禍によって二極化したように思います。まず1つは、ポータルサイトに対抗するため安価な葬儀プランを設定したところ。これでは当社の利益も薄くなり、依頼側・受注側双方ともに疲弊してしまいます。もう1つは、よりいいものを提供したいとするところ。当然プランの設定は高くなりますが、当社もいいものを提供するように努めることになりますから、お客様の満足度は上がるとともに当社の利益も確保することができます」(三村社長)
一方、安価な葬儀プランの場合、小さな祭壇となるので高い技術力は必要としない。「小さい祭壇は、毎回同じようなデザインが中心となります。より高度な技術を要する祭壇受注がないと、必然的にスタッフの挿花技術を高めることができなくなります」と、三村社長は危惧する。その点で大型葬の祭壇は多数の花材を使用し、さまざまな技術を必要とする。こうした大型葬の祭壇に、たとえ補助であっても関わることで、少しずつ技術を習得できるのは、同社のスタッフとしても魅力だろう。「私が祭壇制作をはじめた頃は、仕事はたいへんでしたが楽しかったですし、やりがいを感じていました。ところが、いまの若いスタッフは仕事を楽しめているのか。やりがいを感じているのかというと疑問です。高度な技術を要する祭壇受注が少なければステップアップすることもできず、その結果やりがいを感じることもなく、いずれ辞めてしまうかもしれません」と、三村社長は次世代に対する危機感をもっている。
こうした危機を乗り切るため、三村社長は人材育成、技術継承のための養成機関を年内に設立する意向。すでに、数社の生花業者に声をかけており、三村社長が著した本を教本とした技術講習会を開催し、生花祭壇設営の醍醐味を伝えていきたいとしている。
月刊フューネラルビジネス10月号「特集|生花装飾 次の一手」では、SunVillageのほか、計9社に取材を実施。各社の取組みを豊富な写真とともにレポートする。